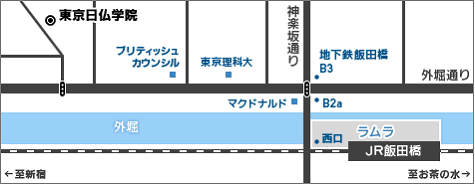日仏経済交流会(パリクラブ)主催
在日フランス商工会議所(CCIFJ)共催
サルコジ氏が率いるフランス新政権は、若者の雇用を増やすために経済成長率を高めることが課題になってきます。日本では安倍政権が急速に進む人口高齢化に直面し、潜在成長率の引き上げを図っています。
4年間にわたり日本を観察し、この夏にフランスに戻られる財務参事官のステファン・オストゥリ氏から個人の立場で、こうした課題に対して財政政策が果たすべき役割について分析をしていただきます。
講演の後、質疑の時間も充分とっておりますので、皆様のご参加をお待ちいたします。
| 日時 | 2007年6月5日(火)18:30~21:00 |
|---|---|
| プログラム | 18:30~20:00 講演・Q&A 20:00~21:00 ブュッフェ |
| 場所 | メルシャン・サロン(メルシャン本社1階) 中央区京橋1-5-8 TEL:03-3231-5600 |
| 最寄り駅 | 銀座線京橋駅または東京駅 |
| スピーカー | ステファン・オストゥリ財務参事官・フランス大使館経済部次長 |
| 司会 | 久米五郎太(パリクラブ会長代行、日揮(株)常勤監査役) |
| 使用言語 | フランス語(質問は英語も可) |
■ご報告
- 講演・質疑は1時間半にわたってフランス語で行われ(一部質疑は英語)、多数のグラフや表が用いられた。
以下にポイントをまとめるとともに、用いられたスライドも添付したので詳細はそれらも参照願いたい。なお、講演者や司会の意見はいずれも個人の資格でおこなわれたものである。 - スピーカー・オストゥリ氏の講演要旨( 資料1参照【PDF形式:4.77MB】)
フランスと日本はこの10年間で経済成長が減速した2つの国である。米国に比べると、
(1) 両国とも労働力人口(15-64歳)の比率は殆ど同じだが、
(2) フランスは就業率や就業時間が10-15%低く、
(3) 日本は労働時間が少し長いものの労働生産性(時間当たりGDP)は29%も低く、
(4) その結果両国とも一人当たりGDPはおおよそ30%近く米国の水準より低い。
日本は、かつては若い国であったが、2000年には老人の比率がフランスを超え、今後更に老人の比率が高まる。フランスも先進国の平均よりは老齢化が早く 進む。しかし、フランスの出生率は94年頃より上昇しており、今や2を超え、EUの中ではトップ・レベルに。家族手当が充実しているほかに、小学校の終業 時間が16時半と遅いことも出生率を高めるのに貢献している。
フランスでは人口が現在の62百万人から、2050年には3百万人増加すると見られているが、労働力人口が支えるべき若年・老年層の比率は今後上昇する。 フランスの失業率は日本よりはるかに高く、55-64歳の層での就業率は日本と異なり非常に低い。また若者(15-24歳)の就業率も低いが、ここは教育 を受けている層が多いことも影響している。
フランスの強い点は労働生産性が米国よりも高いことである。また、経済は国際的に開放され、フランスは外国企業の進んだ生産技術などを導入している。これ はGDPに占める貿易比率、対内・対外直接投資額などを見ても明らかである。弱い点はイノベーションの遅れであり、R&Dの比率が日本などに比し て低い。
財政面ではフランスは日本に比べると、支出規模が大きく、国民負担率(税金・社会保険料)の比率が高く、公的部門の雇用者が多い。両国とも財政赤字が続 き、債務残高がGDP比で増加、特に日本は急膨張した。今後両国とも財政支出を抑制せねばならず、成長加速や雇用増大のために財政政策を活用する自由度が 減少している。
雇用政策との関係では、フランスでは公務員の数が既に減少しており、限界国民負担率と低所得者層への影響、補助水準のあり方が政策面では議論されている。 イノベーション戦略としては投資拡大や研究促進のための支出・税制措置を講じており、05年10月には66のクラスターを育成する決定をおこなった。日本 に倣うものが多い。
結論。フランス・日本はいずれも難しい課題に直面している。すなわち、両国共に財政状況悪化のもとで人口が高齢化し、日本では低生産性、フランスでは低い 競争力が問題になっている。それに対処すべく、フランスでは人口を増加させ、国際的に開放を進めている。日本はイノべーション政策により経済を活性化し、 経済成長の高い地域とのインテグレーションを進めている。 - この後、司会者より資料を使い、レジュメと日本の事情についての簡単な補足説明がおこなわれた。
用いた数字は主としてOECDの2005年データ。( 資料2参照【PDF形式:1.21MB】)
この10年間、日本の成長率は極めて低く(年平均1.15%)、OECD30カ国中30位。米国との一人当たりGDPの差についての図をみると、フラン ス・日本がだいぶ下のほうに並んでおり、その要因としてはフランスの低い就業率、日本の低い労働生産性が浮き彫りになっている。
日本は今後高齢化が進むので、政府は中期的な成長率を1.5%程度、うまくいって2.5%程度とみており、目下如何に労働生産性を上げるかが大きな課題。 政府内の議論では、5年で50%引き上げという目標もだされているが、生産性は急にはあげられない性格のものであろう。労働力供給増大のためには、パート タイムの雇用が多い女性労働力の活用が必要であり、外国人移民労働力(0.3%)の利用もデリケイトだけれど検討課題。
財政面では総債務残高がきわめて高い比率(今年度末にはGDP比148%)となっており、比率が安定し、さらに減少が始まるのはあと7年前後と見られてい る。しかし、ネットの残高では相当低いこと、国債は大部分を日本人が保有していることから、あまり心配しなくてよいとの意見もある。ただ、政治家や国民は 楽観的すぎるのではないか。 - 質疑応答では、
(1) この10年間G7で最もパフォーマンスがよかった英国では、物価安定を目標とした金融政策が奏功したと評価されているが、そうした観点から欧州中央銀行の政策をどうみるか(フランスでは政治家やマスコミに批判があるが)
(2) サルコジ新政権の下で政策は変化するか
(3) 少子高齢化対策として財政政策はどの程度効果があるか
(4) 人口構造の変化に対応した租税政策のあり方――フランスはTVAを古くから導入し、税率も引き上げているが、租税収入に占める割合は一時の40%から現在は25%に下がっている――、
その他移民政策、R&Dが話題になった。 - 本講演会を企画し、司会をおこなったものとして、3点印象を述べたい。
日本の経済政策にとって、フランスは日頃あまり注目されていない。しかし、OECD諸国の国際比較をすると、日仏両国は最近年は少し改善してきたが、 2005年までの過去10年間は低成長にあえいできたという点で共通点がある。また政府の主導性が強いという点でもよく似ている。フランスは硬直的な労働 政策・思い切った経済構造改革への抵抗など大きな問題を抱えているが、他方で最近進めてきた、EUをベースにした国際経済への対応、出生率引き上げ、財政 規律の強化などの政策は日本として目指すべきものである。勿論IT活用などで労働生産性引き上げに成功した米国、グローバル化をテイクチャンスした英国に 学ぶことも少なくないが、日仏を比較しながら今後の経済の進路や経済政策のあり方について考えることは実りが大きいように思われた。
パリクラブではこの2-3年、「フレンチ・パラドックス」や「フランス経済社会モデルの有効性」をテーマに講演やディスカッションを実施してきた。今回の 企画はその延長線上にあり、時間は限られていたが、幅広く基本的な問題をカバーしえたと思われる。サルコジ新政権は経済財務省に労働も分担させ、目下超過 勤務部分への社会保険料・税金免除や社会保障費をカバーするためのTVA導入などが議論され始めている。日本でも夏の参議院選挙後は税制改革が歳出削減と ともに大きな議論になると思われる。資料2のP7は両国の税収構造を比較したものであるが、グローバルな競争の中で、国際的な税制のハーモナイゼイション が重要な視点となっている。今後両国がどのような議論をおこない、政策決定に至るのかは大変興味深い。
参加者は57名。共催者のCCIFJからはラショッセ新会頭、またフランス大使館経済部からはヘッドのバジョン公使が参加し、両機関から多数の参加者が あった。パリクラブからも関本会長を始め、5月末に新たに就任した姉崎経済社会委員長、澤田副委員長など多くの会員が参加し、講演会の後はブッフエの場に 席を移して、懇談が行われた。
(文責:久米五郎太)

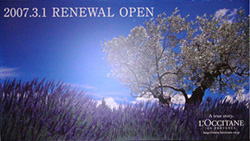 日本に進出してきているフランス企業は、それぞれのブランドや商品・サービスの特性に応じてマーケティングと販売を行っています。CAC40に属する国際的 な大企業や長い歴史を持つラグジャリー企業の活動は比較的よく知られていますが、中小・中堅企業のなかにも特徴のある活動を行っているところが少なくありません。
日本に進出してきているフランス企業は、それぞれのブランドや商品・サービスの特性に応じてマーケティングと販売を行っています。CAC40に属する国際的 な大企業や長い歴史を持つラグジャリー企業の活動は比較的よく知られていますが、中小・中堅企業のなかにも特徴のある活動を行っているところが少なくありません。



 原油の需給が著しくタイトになり、原油価格も緩んで来つつあるとは言え、依然高水準にある。今後の世界のエネルギー市場はどう展開して行くのだろうか?近 年、スーパー・ジャイアント・オイル・フィールドなどの大規模油田の発見は殆どなく、世界の石油生産量はピークを迎えるのではないかというピークオイル・ セオリーがいよいよ現実味を帯びて来ている。また最近脚光を浴びているバイオ・エタノール等の代替エネルギーはエネルギー需給の緩和にどの程度有効なのだ ろうか? 新規油田、ガス田開発の為に今メジャーはどのような新技術を用い、どのような努力をしているのだろうか? 今回の講演では、このような疑問点に 焦点を当て、専門家のドメスティエ氏にお話し頂きました。
原油の需給が著しくタイトになり、原油価格も緩んで来つつあるとは言え、依然高水準にある。今後の世界のエネルギー市場はどう展開して行くのだろうか?近 年、スーパー・ジャイアント・オイル・フィールドなどの大規模油田の発見は殆どなく、世界の石油生産量はピークを迎えるのではないかというピークオイル・ セオリーがいよいよ現実味を帯びて来ている。また最近脚光を浴びているバイオ・エタノール等の代替エネルギーはエネルギー需給の緩和にどの程度有効なのだ ろうか? 新規油田、ガス田開発の為に今メジャーはどのような新技術を用い、どのような努力をしているのだろうか? 今回の講演では、このような疑問点に 焦点を当て、専門家のドメスティエ氏にお話し頂きました。