日仏経済交流会(パリクラブ) 主催
在日フランス商工会議所(CCIFJ) 共催
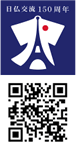 サルコジ大統領は、「過去との断絶」(Rupture)を標榜し、矢継ぎ早に革新的な政策を発表しています。その政治哲学は英国のサッチャーを思わせ、アン グロ・サクソンのメディアはサッチャリズムを連想しているようです。特にフランスの硬直的な労働市場の改革に有効な手を打てるかどうかが最大のチャレンジ の一つだと思われます。
サルコジ大統領は、「過去との断絶」(Rupture)を標榜し、矢継ぎ早に革新的な政策を発表しています。その政治哲学は英国のサッチャーを思わせ、アン グロ・サクソンのメディアはサッチャリズムを連想しているようです。特にフランスの硬直的な労働市場の改革に有効な手を打てるかどうかが最大のチャレンジ の一つだと思われます。
また先日、同大統領は二人のノーベル賞経済学者(スティグリッツ、セン両氏)の協力を仰ぐ事を発表しました。
今回のデバでは、サルコジ大統領の経済政策について、フランスと日本の二つの視点から分析することにより、理解を深め、その行方についても考察しました。
またサッチャリズムとの比較についても議論致しました。
| 日時 |
2008年3月7日(金)18:45~21:15 |
|---|
| スピーカー |
中島厚志氏
みずほ総合研究所 専務執行役員チーフ・エコノミスト
ジャン・バルテレミー氏
ジャン・バルテレミー・コンサルタンシー代表取締役、元DATARアジア代表 |
|---|
| コメンテーター |
ルイ・ミシェル・モリス氏
経済公使 在日フランス大使館 |
|---|
| アニメーター |
沢田義博氏
パリクラブ理事、帝国ピストンリング(株)常勤監査役 、富士銀行元パリ支店長 |
|---|
| プログラム |
講演会:18:45~20:15
懇親会:20:15~21:15(ビュッフェ形式) |
|---|
| 使用言語 |
仏語 |
|---|
| 場所 |
メルシャンサロン
中央区京橋1-5-8メルシャン本社1階 明治屋並び
Tel:03-3231-5600 |
|---|
| 最寄り駅 |
東京メトロ銀座線京橋駅またはJR東京駅 |
|---|
■ご報告
(以下、パネル・メンバーの敬称略)
沢田:サルコジ大統領は、「過去との断絶」(Rupture)を標榜し、矢継ぎ早に革新的な政策を発表しています。その考え方は英国のサッチャーを思わせ、アングロ・サクソンのメディアはサッチャリズムを連想しているようです。
今回のデバでは、サルコジ大統領の経済政策について、フランスと日本の二つの視点から分析することにより、理解を深め、その行方についても考えてみたいと思います。
先ず初めにサルコジ大統領について、私の個人的な思い出を二つお話したいと思います。
- 2000年に、数人のフランス人の友人と共に、サルコジ氏と夕食を共にする機会がありました。当時はジョスパン首相の社会党政権下でした が、既に彼はRPRの有力者でした。夕食を摂りながら、約3時間以上、自由に議論しました。例えば、週35時間労働問題、労働市場の硬直性、公共部門のス ト等々。様々な論点で、我々と考え方に大きな差が無い事がはっきりしました。支持できる議員だと感じましたが、当時は彼が共和国大統領になるとまでは私は 感じませんでした。
- 2003年に、MEDEF(フランス経団連)の夏期大学に出席した時のことです。多くの大臣が講演者として呼ばれていました。当時サルコ ジ氏は既に内務大臣で、人気もありました。驚いた事に、彼が講演の為、ホールに入って来るや否や、自動的に出席者全員のスタンディング・オヴェイションと なり、大きな拍手が巻き起こりました。 他の大臣が入場した時はそんな事は起きませんでした。 この時、私はこの人がシラク大統領の後継者になるかもしれ ないと感じました。そして、現在では、彼はHYPERPRESIDENTと呼ばれています。
さて、ここで3つの問題提起を行いたいと思います。
- グリーンスパン氏はその回想録の中で、フランス経済の将来について悲観的な事を言っています。その理由はフランスの市場が自由で開放的な 市場となっていない事(フランス人の36%しか、このタイプの市場に賛成していません)。そして、グローバリゼーションに熱心ではない事です。
事実サルコジ大統領自身も自分の主義はLIBERALISME REGULE (ある程度の規制や国家介入を認める自由市場主義)と述べています。
但し、グリーンスパン氏はサルコジ大統領には期待感を持っているようです。2004年に両氏が会った時、大統領はアメリカ経済モデルの柔軟性を賞賛しているからです。
サルコジ大統領はグリーンスパン氏の期待に応えられるでしょうか?
- フランスの労働法は労働者の権利を強く保護しています(おそらく西欧では一番)。この為、フランス企業は常に新規の雇用には非常に慎重です。以前、レイモン・バール元首相は講演で、フランスの最大の問題点は労働市場の硬直性(例えば、解雇が難しい)にあると言っています。
サルコジ大統領はこの問題を解決できるでしょうか?おそらく大統領の最大のチャレンジです。
- 現在までの大統領の組合との交渉姿勢は、サッチャー元首相の改革努力を思わせます。特に1984-85年の最も過激な鉱山労働者組合との戦いです。最終的に彼女は勝利を収めました。
サルコジ大統領はフランスの組合の説得に成功するでしょうか?
バルテレミー(講演):
「サルコジ大統領経済政策の三つの主要な分野:改革、労働市場、購買力」
- 経済指標については新規雇用者が昨年約99千人増加している事が注目されます。
事実失業率は2007年第4四半期で1983年以来最低の7.5%にまで低下しました。これは大きな成果です。一方輸入増大の為、国際収支が悪化しています。
- 「もっと働き、もっと収入を増やす」が大統領の選挙スローガンです。労働市場については、本年1月に「労働市場近代化の為の合意」が成立 しました。例えば、試用期間の1ヶ月延長、職業間の移動を活発化させる事、高年層の雇用機会の開拓などです。また、デンマークに範をとった、 “FLEXICULITE”という考え方を検討しています。産業の変化の激しい今日、欧州の先進国では大体15%が失業し、15%の新規雇用が行われてい ます。従って、解雇を容易にし、一方新規雇用についても積極的に行うと言う考え方です。政府が音頭を取る事になります。
- 購買力の増加については、彼は選挙公約として「私は購買力大統領」だと大見得を切っています。この点については既に昨年8月に “PAQUET FISCAL”と呼ばれるTEPA(労働、雇用、購買力)向上のための税制改革を実行済みです。例えば、週35時間労働に関する休暇RTTの未消化分の買 取、住宅ローン金利の税額控除、時間外賃金の非課税化などです。
国際面では、
- ユーロの為替レートの水準について欧州中央銀行との論争
- 財政均衡のEU基準への復帰の延期(2010年から2012年へ)
- 産業界のリストラへの政府の介入(フランス企業のみならず、フォード、ミタル・アルセロールなど)
最後にアタリ委員会提言(本年1月23日報告)についてお話します。300件を超える膨大な件数の政策提言をしていますが、本日はその中の数点について触れます。
- 中小企業支援策
・政府、大企業による付加価値税の中小企業向け支払を1ヶ月以内とする。
・行政当局による対応の迅速化 など
- 完全雇用の実現
・組合、経営者団体に係わる規則の近代化
・若年者雇用の強化(全ての企業、公的部門に従業員の年齢構成報告を義務付け)
・高齢者雇用の強化(65歳からの年金引き上げ) など
- 諸既得権の削減、地域間移動の奨励
- 現在の世代の生活水準維持を次世代の負担とはしない。
公共部門の支出減少を2008年より開始し、2009年からGDPの1%の支出を減少せしめる。 など
2012年のフランス(中期的視点)
2008年4月よりの改革が着手されると、次のような目標が達成されると考えます。
- 現在のGDP予想成長率に比し、更に1%増加
- 失業率は5%に低下
- 2百万戸以上の住宅建設
- 公的負債がGDPの55%に低下
- フランスへの観光客数が年90百万人に増加(現在は70百万を上回る水準)
沢田:質問1.サルコジ大統領はアタリ委員会に「貴委員会の提言は全て実行します。」と約束していますが、実際には彼は地方の県の廃止や、薬品業界 の規制緩和に反対していると言われています。従って、全ての提言は実行されない可能性があります。どの程度の提言が実際に実行されるとお考えですか?
バルテレミー:大統領自身はこのアタリ委員会の提言以外にも、多くの提言を受けています。そして、それらの多くの点について実際にコミットしています。彼は意見の対立を放っては置けない性格なので、意見の相違点があっても何らかの解決策を見つけ出すと思います。
沢田:質問2.サルコジ大統領は2008年、つまり年内に週35時間労働制を事実上撤廃しようと希望していると言われています。実現可能性は?
バルテレミー:個人的には実現すると思います。この発言は今年一月の年頭記者会見のものですので、あくまで彼の希望だと思いますが、既にその方向で RTTの買取や残業時間に係わる社会保障費の削減、免除等の政策が採られています。今後更に具体的な政策が発表されると思います。
中島(講演):「サルコジ大統領の経済政策の基本的な考え方」
1) サルコジ大統領は新自由主義者か? 或いは統制経済主義者か?
- NEOLIBERALISME(新自由主義)の定義
自由と個人の責任の原則に立ち、市場経済をベースとし規制緩和、小さな政府(公共部門の縮小、民営化など)を指向。
- DIRIGISME(統制経済主義)
政府が経済の方向、政策決定に大きく関与。
筆者注:欧州とアメリカでは「リベラル」と言う言葉の意味が異なる事に、ご注意下さい。アメリカでは「リベラル」と言うのは民主党左派の政策、即ち「社会民主主義的傾向、大きな政府」を意味します。)
- 新自由主義の例:サッチャリズムとレーガノミックス
A.サッチャー首相の主要な政策
- 金融財政市場 ― 為替管理法撤廃、ビッグ・バン、社会保険法改革
- 民営化 ― BP, British Aerospace, British Telecom, British Gas, BA, Rover, Rolls Royce, etc
- 労働市場 ― 80年雇用法(クローズド・ショップ制廃止)など
- 小泉首相の主要な改革(サッチャリズム的)
- 金融市場の活性化 ― 不良債権の大幅な削減
- 産業の活性化 ― 産業再生機構の設置により、ダイエー、カネボウ等のリストラを支援
- 規制緩和 ― 1000件を超える規制を緩和
- 郵政民営化
- 社会保障改革
- 地方行政改革(地方分権化推進)
- 政府系金融機関改革、再編
- サルコジ大統領の改革
彼の考え方はかなりリベラルですが、サッチャリズムとは異なります。
- 自由な市場経済 ― 国家の介入を辞さない。
- 小さな政府 ― 明確な政策なし。
- 民営化 ― 明確な政策なし。 などが相違点です。
サルコジ大統領の考え方は多くのフランス人の意図を反映しているものと考えられます。即ち、新自由主義的改革の必要性に理解を示しながらも、その実行に躊躇しているのです。その状況は現在の日本に良く似ていると考えます。
2) 日本と比べたフランス経済の強みを列記します。
- 増加しつつある人口
- 政府の財政赤字が日本に比べ小さい
- EUの存在
- 市場経済のメカニズムがより浸透している
沢田:質問3.フランスは欧州諸国の中では国営企業の対GDP比率が最も高くなっています。ただ今の中島さんのプレゼンでも?が付されていました が、民営化についての大統領の考え方をお聞かせ下さい。 もし前向きであるならば、どの程度のテンポで推進するつもりなのでしょうか?
モリス:フランスでは既に、民営化推進はサルコジ大統領以前から政府の方針となっていますから、サルコジ大統領もその方針は変えないはずです。市場の状況を睨みながら、タイミングの良い時により高い株価で売却すると思います。
以下、フロアからの質問
檜山氏(CHROMagar):(質問)サルコジ大統領の政治哲学についてはどう考えれば良いのでしょうか?どうも政治哲学は無いように見受けられますが。
バルテレミー:大統領の政治哲学は、しいて言うならプラグマティズムだと思います。 彼の行動はイデオロギーを超えています。アタリ氏やベッソン氏は Socialste ですが、彼らの意見もどんどん取り入れています。
中島:小泉首相の政策も似ていました。彼の政策は結果的には新自由主義的でしたが、彼の真の意図は自由民主党の改革にあったのではないかと思います。
ルシュヴァリエ氏(日仏会館): 世界の中で、フランスと日本二カ国が必ずしも リベラルではない資本主義国だと思います。今後この二か国はアングロ・サクソン的な資本主義、新自由主義の方向に収斂して行くのでしょうか?
中島:日本やフランスが今後アメリカ的な新自由主義に収斂するとは思いません。 世界は多極主義とも言うべき多元的な方向に向かうでしょう。各国は市場メカニズムをベースとしながら、自国の特長やスタイルを活かした形の資本主義を採用して行くと考えます。
久米氏(パリクラブ会長代行):最近サルコジ大統領の支持率が低下傾向にあり、一方フィヨン首相の支持率は上昇しています。大統領とその政策の実行者である首相の支持率に大きな差が出ている事について、どうお考えですか?
バルテレミー:支持率は単なるバロメーターに過ぎないのですが、マスコミや社会により多くさらされている方が、より多く批判を受けるリスクにさらさ れます。まさにサルコジ大統領のケースです。 現在フィヨン首相はサルコジ大統領のアシスタント的な動きしかしていません。おそらくそれが原因ではないか と思います。
沢田:それでは、ここでモリス公使にこの講演会のまとめをお願いします。
モリス:議論が多岐に亘っているので、まとめる事はかなり難しいのですが、感じた点をいくつか述べてみたいと思います。
- まずサルコジ大統領とフィヨン首相については、今年来日が予定されていますので、その時に実際に皆様に感じて頂きたいと思います(フィヨン首相:4月11,12日、サルコジ大統領:7月初め)。
- フランスではサッチャリズムやレーガノミックスは余り人気がありません。特にレーガノミックスは大減税の結果、その後ものすごいインフレを招いたからです。
- 市場原理主義については危険だと思っています。
- シュンペーター流の「創造的破壊」についても、慎重な対応が必要でしょう。当時と比べると技術の進歩や多様化が比較にならない程加速化し ています。結果として失業者の急増を招き、国民は保護主義を求めるリスクがあります。国内企業の収益の維持に気配りする必要もあるでしょう。
- 私が考える真のLIBERALISME とは国境の廃止であり、EUは過去50年以上にわたり、その為の努力を続けてきた結果、今やそのGDPは世界一になりました。最近EUに加盟したポーランドなどは驚くべき経済成長を続けています。
- 私の担当分野である国際貿易について最後に述べます。 フランスの経常収支の赤字については、余り気にしてはおりません。なぜなら、現在 のフランスの強みはサービス産業(例、ホテル産業)にあり、経済成長の最大の原動力となっているからです。 サービス産業は必ずしも経常収支には貢献しま せん。
以上
(文責:沢田 義博)

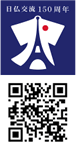 サルコジ大統領は、「過去との断絶」(Rupture)を標榜し、矢継ぎ早に革新的な政策を発表しています。その政治哲学は英国のサッチャーを思わせ、アン グロ・サクソンのメディアはサッチャリズムを連想しているようです。特にフランスの硬直的な労働市場の改革に有効な手を打てるかどうかが最大のチャレンジ の一つだと思われます。
サルコジ大統領は、「過去との断絶」(Rupture)を標榜し、矢継ぎ早に革新的な政策を発表しています。その政治哲学は英国のサッチャーを思わせ、アン グロ・サクソンのメディアはサッチャリズムを連想しているようです。特にフランスの硬直的な労働市場の改革に有効な手を打てるかどうかが最大のチャレンジ の一つだと思われます。