日仏経済交流会(パリクラブ) 主催
在日フランス商工会議所(CCIFJ) 共催
2007年、2008年度の新規入会者との会合を開催致しました。新メンバーの職域と年齢は多岐にわたり、当会に対する抱負や希望について情報交換致しましたことは、今後の活動に大いに有益だと存ずる次第です。
| 日時 | 2009年3月13日(金) 18:30~ |
|---|---|
| 場所 | 八芳園 〒108-8631 東京都港区白金台1-1-1 03-3443-3111(代表) |
| 最寄り駅 | 地下鉄【南北線・三田線】白金台 および【浅草線】高輪台 http://www.happo-en.com/access/index.html |
■ご報告
 2009年3月13日(金)18時半から、ツグミの来る庭が自慢の八芳園スラッシュカフェで、第55回ランデブー・フランコジャポネ開催。
2009年3月13日(金)18時半から、ツグミの来る庭が自慢の八芳園スラッシュカフェで、第55回ランデブー・フランコジャポネ開催。
パリクラブ会員とCCIFJ会員約80名が集いました。パリクラブの福本しのぶ会員の竪琴演奏に続く、磯村名誉会長とラショッセ会頭共同の乾杯音頭のあ と、三浦一雄パリクラブ副会長お心入れのローヌ、ボルドオ、ラングドック(白)と八芳園ブッフェを賞味しつつ一同交歓して21時に散会。
07年度・08年度の入会で参会連絡があった次の各氏のお名前を呼び上げて紹介しました(ABC順、敬称略)。
粟野みゆき(仏検1級合格者の会副会長)
遠藤純也(ソニー シニアBluetooth エヴァンジェリスト)
福本しのぶアニエス(Artwide Production経営 竪琴奏者)
長谷川正純(元丸紅)
平林博(日印協会理事長 三井物産・東芝各社外取締役 早大教授 元駐仏大使)
廣瀬真之(元住友商事)
岩崎晃(日建設計顧問 元国際協力銀行)
金山佳正(日本航空執行役員)
樫本幸一(Senior managing Director, Dai-Ichi Life International (Europe) Ltd.)
好田二朗(エアバス シニアディレクター事業開発担当)
楠田友世(日本出版販売 経営戦略室)
宮原英男(大林組 エンジニアリンググループ長)
牟田正明(大成建設国債支店営業担当部長)
中井毅(石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与 元JETROパリ所長)
根津綾子(NHK プロデューサー)
斉藤ゆきみ(ゆきみサロン・ド・サヴォワール・ヴィー)
佐々木敏彦(みずほ証券 アジア・オセアニア投資銀行部シニア・ヴァイスプレシデント)
関口昭成(三菱商事重機ユニット国内統括部長)
七里淳哲(元サントリー取締役ワイン事業部長)
須藤實(みはし開発部長 元丸紅)
竹口淳史(元住友銀行)
内田真人(成城大学社会イノベーション学部教授 元日銀)
 上記に先立ち、関本から、「パリクラブは設立後16年目で現在メンバーは300人。親仏の一点で共通する20歳台前半~80歳代のビジネスマンが、相手方の フランス人と意見や情報を交換できる場として、年に15回程度、特定テーマのコンフェランスや面識と懇親が目的のランデブー・フランコジャポネを実施。こ れらのイベントにCCIFJの事務協力が期待できるが、その着想と実施はすべて会員の発意と貢献に懸かっている。現預金が資産の総てでいわゆる事務所を持 たない。意思決定にはインターネットを多用している」などと説明。なお、最近のイベントの実例として、「日仏経済関係150年の回顧と展望プロジェクト」 として行った、「フランス語ビジネスの実態調査」「ワインを巡る日仏経済交流」「財政・金融面の日仏交流」「第三国における日仏協力」「直接投資に係わる 日仏交流」を挙げ、協力者に謝辞を呈しました。
上記に先立ち、関本から、「パリクラブは設立後16年目で現在メンバーは300人。親仏の一点で共通する20歳台前半~80歳代のビジネスマンが、相手方の フランス人と意見や情報を交換できる場として、年に15回程度、特定テーマのコンフェランスや面識と懇親が目的のランデブー・フランコジャポネを実施。こ れらのイベントにCCIFJの事務協力が期待できるが、その着想と実施はすべて会員の発意と貢献に懸かっている。現預金が資産の総てでいわゆる事務所を持 たない。意思決定にはインターネットを多用している」などと説明。なお、最近のイベントの実例として、「日仏経済関係150年の回顧と展望プロジェクト」 として行った、「フランス語ビジネスの実態調査」「ワインを巡る日仏経済交流」「財政・金融面の日仏交流」「第三国における日仏協力」「直接投資に係わる 日仏交流」を挙げ、協力者に謝辞を呈しました。
以上

 昨年に引き続き、文政4年(1821年)創業184年という長い歴史をもつ酒蔵の名門「寒梅酒蔵株式会社」(銘酒「飛翔天」は2004年10月関東信越国税局管内鑑評会で最優秀賞を受賞)を訪ねました。参加者30名、日仏でほぼ相半ばでした。
昨年に引き続き、文政4年(1821年)創業184年という長い歴史をもつ酒蔵の名門「寒梅酒蔵株式会社」(銘酒「飛翔天」は2004年10月関東信越国税局管内鑑評会で最優秀賞を受賞)を訪ねました。参加者30名、日仏でほぼ相半ばでした。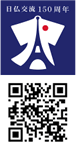 早稲田大学客員研究員、ナタリー・カヴァザンは1996年の来日以来地理学博士としての研究の傍ら、日本の伝統芸術に興味を抱き学び続けています。
早稲田大学客員研究員、ナタリー・カヴァザンは1996年の来日以来地理学博士としての研究の傍ら、日本の伝統芸術に興味を抱き学び続けています。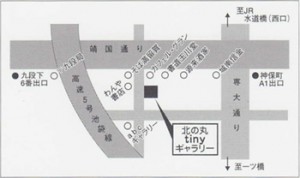

 11月27日(木)に日本財団の会議室で、日仏経済交流会(パリクラブ)と在日フランス商工会議所の共催で「個人競技の国・日本と団体競技の国・フランス」と題して講演会が開催され、30名の聴衆が集まった。
11月27日(木)に日本財団の会議室で、日仏経済交流会(パリクラブ)と在日フランス商工会議所の共催で「個人競技の国・日本と団体競技の国・フランス」と題して講演会が開催され、30名の聴衆が集まった。 これに対してヴェルディエ氏から「日本語の辞書にそもそも団体主義と言う単語はない。日本人は個人の技術、スキルベースは優れているが、それを団体の中で活 かす能力はない。したがってラグビーやサッカーなどの団体競技におけるパフォーマンスは低い」というスピーチがあった。
これに対してヴェルディエ氏から「日本語の辞書にそもそも団体主義と言う単語はない。日本人は個人の技術、スキルベースは優れているが、それを団体の中で活 かす能力はない。したがってラグビーやサッカーなどの団体競技におけるパフォーマンスは低い」というスピーチがあった。