 6月6日夕、フランス大使公邸における第6回ソワレ(ランデブー・フランコジャポネ)で、フォール大使がなさった演説につき、このほど公表の承認を得ましたので訳文とともにサイトに掲載致します。
6月6日夕、フランス大使公邸における第6回ソワレ(ランデブー・フランコジャポネ)で、フォール大使がなさった演説につき、このほど公表の承認を得ましたので訳文とともにサイトに掲載致します。
このソワレは、日仏関係150周年と当会設立15周年を記念して開かれました。当日の模様については、当ページ掲載の写真と下記のプログラム(フランス語)ならびに関本会長挨拶をご参照下さい。
なお、このプログラム内にて、当会のあゆみと活動内容、それに、本年2月のビジネスにおけるフランス語使用状況の調査結果を踏まえた日仏経済関係強化に関する10の提案を披露しました(久米会長代行説明)。
冒頭乾杯の音頭をおとり戴いた在日フランス商工会議所ラショセ会頭に深く感謝申し上げます。醵金に応じて下さった皆さまに厚く御礼申し上げます。尺八と竪琴を演奏して戴いた福本しのぶ様と安島瑶山師にあらためて拍手をお送り下さい。
218名の参加を得た収支の内訳は次の通りでした。
+199千円の収支尻につき、日本パスツール協会宛寄付金(30千円)と当日フォール大使が強調されたVolontariat international en entrepriseを始めとする日仏青年交流関係に役立つ費用に充当することにしたく、先般当会理事会の承認を得ました。
| 醵金収入 |
805 |
(単位:千円) |
|---|
収入計
支出計
ディネ・ビュッフェ負担費用 |
805
606
429 |
(単位:千円) |
|---|
奏楽関係費用
損害賠償責任保険料
会議費
印刷費
通信運搬費
差引収支 |
805
606
5
24
18
+199 |
(単位:千円) |
|---|
■PROGRAMME
DE LA SOIREE DU PARIS CLUB
(Groupe économique Franco-japonais)
Vendredi 6 juin 2008
18h00 : Ouverture
Discours de Son Excellence l’Ambassadeur de France au Japon
Remerciement du Paris Club, M. Kanji Sekimoto, Président
Présentation des activités du Paris Club, M. Gorota Kume, Président adjoint
Kampai par Monsieur Michel Lachaussée, Président de la CCIFJ
Concert :
duo de syakuhachi (Yôzan Ajima) et d’harpe (Shinobu Fukumoto)
Cygne (Saint-Saens),
La mer de printemps (Michio Miyagi),
Claire de lune (Debussy),
Medley de chansons japonaises
Buffet dînatoire
20h45 : Fin de la soirée
Présentation du PARIS CLUB (Groupe économique Franco- japonais)
Le Paris Club est une association à but nonlucratif, née en avril 1993, qui a pour but de développer les relations économiques franco-japonaises en facilitant les échanges de points de vue entre les hommes d’affaires japonais et français. Sa fondation, suggérée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon (CCIFJ), a été lancée par des Japonais ayant travaillés en France dans les années 1980. Depuis lors les adhérents proviennent de domaines économiques divers tel que la finance, le commerce, l’industrie, le service, la presse, les missions commerciales et financières, etc.
Le Paris Club organise des événements socio-économiques et culturels, très souvent avec l’appui de la CCIFJ et de la Mission économique, et dans quelques cas avec le soutien d’autres organismes tel que la Maison franco-japonaise. Près de 15 événements par an sont organisés : débats cocktail dînatoire, voyages d’études, réunions titulaires rendez-vous franco-japonais… Le nombre total d’événements organisés par le Groupe depuis le début de ses activités s’élève à 150. Les membres du Paris Club sont des individus de tout âge : de 27 à 78 ans. Il compte actuellement 297 membres, dont 35 administrateurs. Les quatre comités - socio-économique, culturel, régional et jeunesse - composés des administrateurs organisent des événements en mettant à contribution leurs connaissances profession- nelles ainsi que le temps aménagé autour de leurs travail respectif.
Activités du Paris Club
Le Paris Club a récemment organisé des débats dont les principaux thèmes ont été la politique économique du Président Nicolas Sarkozy, le Biopôle de Lyon, Asie et Japon, l’attractivité de la France et les stratégies d’entreprises face à la globalisation dans les domaines automobile, aéronautique, électrique, cosmétique et d’animation.
Dans le cadre du 150ème anniversaire des relations franco-japonaises, la conférence sur l’aube des échange franco-japonais (Mr. Christian Polak) et la visite de la filature de Tomioka ont été organisées, et le Paris Club a parallèlement étudié « les évolutions des affaires franco-japonaises et l’usage du français dans les affaires » en menant des enquêtes auprès d’une centaine d’hommes d’affaires y compris quelques haut fonctionnaires, universitaires et journalistes, majoritairement japonais, pour retracer l’histoire des relations franco-japonaises et considérer leur futur.
En 2008-2009, seront abordés les sujets suivants : les relations franco-japonaises dans les domaines financier et bancaire, les échanges franco-japonais dans le domaine du vin, les investissements croisés dans le secteur manufacturier, les coopérations franco-japonaises envers les marchés tiers, les atouts et les faiblesses de la France et du Japon sur les plans économiques et technologiques.
Conclusions de l’étude sur les évolutions des affaires franco- japonaises et l’usage du français dans les affaires :
Les échanges franco-japonais ont été beaucoup influencés pendant des décennies par les conjonctures économiques respectives, ainsi que par l’élargissement de l’Union Européenne et la globalisation. Le renforcement des relations bilatérales devrait s’effectuer en tenant compte non seulement des échanges commerciaux et des investissements (directs et portfolios) entre les deux pays mais aussi des relations aux marchés tiers avec des perspectives mondiales.
La promotion du renforcement des rapports va demander l’amélioration des environnements des affaires dans les deux pays ainsi qu’une meilleure connaissance mutuelle des deux pays et des hommes d’affaires qui doivent être des partenaires. Les efforts pour diffuser les vraies images et favoriser l’attractivité de la France et du Japon, particulièrement sur les plans économique, technologique, légal et sur les relations internationales devraient se déployer visant notamment les jeunes et les cadres dans les sociétés ainsi que la classe des dirigeants. Des classes de français dans les universités et des autres lieux pourraient s’adapter à ces besoins. La présentation des aspects variés de la France serait aussi souhaitable.
Même si, comparé à autrefois, l’anglais est devenu une langue plus souvent utilisée entre les Japonais et les Français, les hommes d’affaires japonais ont toujours besoin d’élever leur niveau de français au même titre que l’anglais, pour améliorer la communication avec leurs interlocuteurs français, qui sera la base de bonnes qualités d’affaires et de services. Ce sera réciproque pour les Français qui développent des affaires avec des Japonais. Les systèmes de bourses techniques et les stages devraient s’améliorer et la capacité linguistique du français sera appréciée pour le recrutement par des sociétés.
Propositions pour renforcer la relation économique franco-japonaise :
- L’amélioration de l’environnement d’affaires en France.
- La promotion des coopérations aux marchés tiers dans le contexte mondial actuel.
- L’accélération des dérèglements au Japon.
- L’étude conjointe et la publication des atouts (et des faiblesses) de deux pays dans les domaines économique et technologique
- L’établissement de conférences économiques franco-japonaises destinées aux cadres et jeunes recrutés dans les affaires.
- L’établissement de classes abordant les relations internationales, l’économie, les lois et les affaires du point de vue français, visant les jeunes japonais.
- L’organisation du Mois de la France.
- Le renforcement du système de bourses techniques et de stages.
- La diversification des contenus de l’enseignement de la langue française dans les universités et la promotion des échanges des lycéens et étudiants des deux pays.
- L’utilisation des examens de français à l’échelle nationale pour le recrutement par les sociétés françaises.
■関本勘次パリクラブ会長挨拶
大使閣下ご夫妻
ご列席の皆さま
今晩は。
日仏経済交流会(パリクラブ)を代表して一言申し上げます。
フォール大使閣下ご夫妻、本日は、日仏関係150周年行事の一環としてこのソワレを催してくださる光栄に浴し、まことに有難く一同に成り代わり厚く御礼申 し上げます。私どもは既往に5回同じソワレにお招きいただいて、その都度新しい日仏の出会いを享受して活動の弾みにさせていただきました。本夕もその期待 に胸をふくらませております。
フランコフィルのビジネスマンが個人として会員になって、各自の職業で培った経験を役立てつつ本職とは別の仕事として自主的にパリクラブの活動を行うこ と。この基本方針を堅持して、パリクラブは本年設立15周年の年を迎えました。この間、私どもが専用の事務所を持つことなく催したパネルや見学旅行などイ ベントは150件、この3年間では50件に上ります。その領域は、経済社会関係と文化産業関係に集中的ですが、最近は、両国間の地域間交流と青年間交流に も力を注いでいます。会員数は300名前後の推移ですが、最近は喜ばしくも20歳代~30歳代の人が当会活動に関心を示し始めています。とはいえ、活動を 企画し実行する中心は50歳代~60歳代の会員です。
私どもの活動内容については、この後の発表とプログラムの記載に譲りますが、これまでの活動が、経済に係わる日仏関係の発展になにがしかお役に立ったとす れば、それは、大使館なかんずく経済商務部の助言、在日フランス商工会議所の物心両面にわたる後援、日仏会館を始めとする日仏関係諸団体のご協力があって のことであります。厚く御礼申し上げて今後も相変わらぬご厚誼とご支援をお願い申し上げる次第です。
本夕は大使閣下ご夫妻に、設立以来物心両面に渡ってパリクラブ支えて下さっている在日フランス商工会議所のラショセ会頭を始めとする役員方と事務局の 方々、オスタン様を始めとするフランス政府対外貿易顧問委員(CCEF)の皆さま、それに元駐仏日本大使の木内様と平林様をお招きいただいております。ま た、最近の私どものイベントをご支援いただいた各方面の方々もご出席であります。その中で私がここでお名前を挙げたいのは次の方々であります。毎年の酒蔵 見学先である久喜市の寒梅酒造鈴木逸郎社長、同じく毎年のおみこしかつぎの地元自由が丘の渡辺靖和様、先般の見学先世界遺産候補富岡製糸場を運営されてい る岩井富岡市長、加えて地方の日仏協会から、長野の滝澤様、甲府の今井様、横浜の西堀様、横須賀の鈴木宇土様です。
重ねて大使閣下ご夫妻のご高配に心から感謝申し上げるとともに、日仏関係150周年を機に日仏関係の発展に一層の弾みがつくとを祈念いたします。また、それに私どもがなにがしかのお手伝いできますならば望外の幸せに存じる次第です。ありがとうございました。
Monsieur et Madame l’Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs,
Bonsoir
Monsieur l’Ambassadeur, au nom du Groupe Economique Franco-Japonais (Paris Club) je me permets de vous exprimer, tout d’abord, tous nos remerciements sincères pour votre obligeance de nous donner cette soirée dans le cadre de la manifestation de 150ème Relations Franco-Japonaise. Dans le passé nous avons eu 5 fois de l’honneur d’être invité à la même soirée et chaque fois nous avons été favolisé beaucoup d’heureuses rencontres et avons pu prendre l’élan pour le saut de notre activité. Cette fois-ci nous comptons également sur même chances.
En observant la direction telle que l’adhérent doit être indivuduel et francophile, aussi doit faire ses activités en mettant à contribution ses connaissances professionells ainsi que le temps aménagé autour de ses travaux principaux. Notre Club a organisé, malgré sans espace de bureau, 150 manifestations, socio-economiques ou culturelles au-délà de 15 ans jusqu’à cette année depuis sa création 1993 (dans trois dernières années 50 événements ont été réalisés). Depuis l’an avant dernier les activités à l’échange franco-japonaises de jeunes personnes d’affaire et les activités régionales entre deux pays ont démarré bon. Le Club compte actuellement 300 membres tout au plus. C’est à ma grand joie, que personnes vingtaine et trentaine se sont mise à s’intéresser aux événements de notre Club récemment. Pourtant c’est toujours la actualité que les membres entre ciquantaine et soixantaine sont le pivot de l’élabration et de l’exécution d’un projet.
Monsieur l’Ambassadeur, si nos activités pouvaient serivir aux rapports economique entre deux pays même un peu, nous serions très heureux. Mais ce serai entièrement grâce aux conseils de Misssion Economique de l’Ambassade et au soutien matériel et moral de CCIFJ soit à la coopération de toutes organisations franco-japonaises sur tout Maison Franco-Japonaise. En remerciant d’avance nous voudrions bien solliciter votre faveur pour notre future.
Mesdames et Messieurs, ce soir Monsieur l’Ambassadeur invite Mr Lachussée de CCIFJ, ses Adminisrateurs et son équipe ainsi que Monsieur Gael AUSTIN et Conseillers du CEF. Nous avons l’honaire de présence de Mr. Kiuchi et Mr. Hirabayashi, anciens Ambasadeurs en France. Aussi nous avons le plaisire d’assistance de ceux qui savent toutes circonstances de notre activités récentes. Par example Mr. Iwai Maire de Tomioka, Mr. Suzuki Itsuro PDG de Cave de Saké à Kuki, Mr. Watanabe de Jiyugaoka, Mr Takizawa de Nagano, Mr. Imai de Kofu, Mr. Suzuki Udo de Yokosuka.
Monsieur l’ambassadeur, maintenant je me permets de donner la parole à Mr Gorota Kume mon adjoint, qui va vous présenter le contenu de nos activités.
Monsieur et Madame l’ambassadeur, je vous remercie de votre accueil chaleureux encore. Merci beaucoup de votre attention.
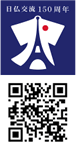 日仏経済交流会(パリクラブ)は、1993年に日仏で経済活動に従事したビジネスマンにより設立されて以来、日仏交流の発展に向けて様々な活動を重ね15年 を迎えました。本年はちょうど日仏交流150周年にあたり、「日仏経済関係150年―回顧と展望」と題する一連の行事を笹川日仏財団の助成も受けて実施し ております。
日仏経済交流会(パリクラブ)は、1993年に日仏で経済活動に従事したビジネスマンにより設立されて以来、日仏交流の発展に向けて様々な活動を重ね15年 を迎えました。本年はちょうど日仏交流150周年にあたり、「日仏経済関係150年―回顧と展望」と題する一連の行事を笹川日仏財団の助成も受けて実施し ております。

 6月6日夕、フランス大使公邸における第6回ソワレ(ランデブー・フランコジャポネ)で、フォール大使がなさった演説につき、このほど公表の承認を得ましたので訳文とともにサイトに掲載致します。
6月6日夕、フランス大使公邸における第6回ソワレ(ランデブー・フランコジャポネ)で、フォール大使がなさった演説につき、このほど公表の承認を得ましたので訳文とともにサイトに掲載致します。



