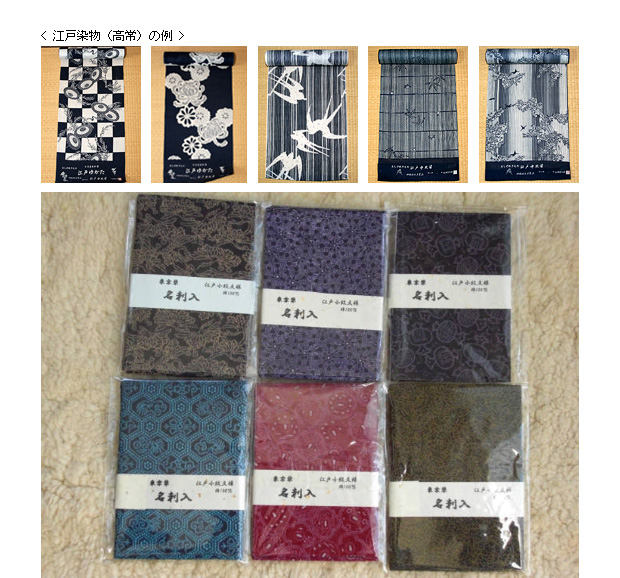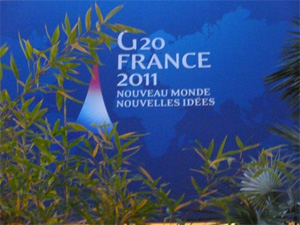日仏経済交流会(パリクラブ) 主催
在日フランス商工会議所(CCIFJ) 日仏会館 共催
笹川日仏財団 協力
【ご報告】
会館501会議室は新年の多忙な時期にもかかわらず約40名の満席となった。フランス人も8人参加。鳥海準教授はパワーポイントを使って約30分、 パリ首都圏整備構想の背景、計画の変遷、』、グランパリ法と構想、現況・批判・展望について説明があった。簡潔で要領のよい講釈であったが、何故、グラン パリ構想がほぼ挫折したプロジェクトになってしまったのかについての言及がなかったのは残念であった。石垣課長補佐は東日本大震災後の都市・地域づくりに ついて安全・安心、線より面、粘り強い構造、インフラ耐震、リダンシーとネットワーク、社会資本の多面的機能、災害に強い都市づくり、東京中枢機能バック アップ、最後に国際競争力のためのアジア・ヘッドクォーター特区等、政府の重点施策が2つの資料を使って報告がなされた。普段、なかなか聞けない内容の講 演であった。東京首都圏に関して「平成22年度首都圏広域地方計画の推進状況について」と題する資料が配布された。東京首都圏については、参加者より、断 熱材、航空管制、PPP、高速道路についての質問があった。
文責・写真撮影 瀬藤澄彦
-

熱心に聴き入る参加者 左に関本前会長
-

右より鳥海講師、石垣講師、臼井通訳、久米会長
【イベント概要】
サルコジ大統領が就任以来かげてきたグランパリ・プロジェクト。首都圏の広域都市連合体をめぐるイル・ド・フランス州議会やパリ市との調整を経て、 パリ首都圏結成構想が今、動き出そうとしている。日本は東日本大震災を教訓に首都圏のあり方をさらに新たな視点から再考することが求めらている。世界最大 のメガシティ東京の都市としての将来の課題と展望はどこにあるのか。同じように集権的な政治構造を特徴とする日仏の首都圏の将来を日本の二人の第1線の専 門家の講演を通じて参加者との意見交換を交えて比較する。
| 日時 | 2012年1月17日(火) 18:30~20:30 |
|---|---|
| 場所 | 日仏会館501会議室 http://www.mfjtokyo.or.jp/ja/access.html |
| 講師 | 鳥海基樹 首都大学東京準教授 石垣和子 国土交通省総合政策局政策課政策調査室課長補佐 |
| 講演 | 『グランパリの枠組みと現状』 鳥海基樹・首都大学東京準教授 『我が国の都市・地域づくり~東日本大震災後の方向』 石垣和子・国土交通省総合政策局政策課調査室長課長補佐 |
| 通訳 | 日仏英語 逐語通訳 臼井久代 |
| 会費 | 無料 |
| お申込み締切 | 2012年1月17日(火)の当日まで受付ます |
| お問い合わせ先 | ご不明な点がございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。 bonjour@parisclub.gr.jp |