
今回の感想をご来場者にお聞きしました。

最初は、飯尾まさ代さんとそのご子息である飯尾愛一郎さんです。
飯尾さんの娘さんもパリクラブ会員で、飯尾さんは以前開催された第1回サロンドパリクラブにもご参加いただいております。
「味の素さんは、早期に欧州へ進出するために、ローカル企業と結びつき、現地で材料を求めて現地生産を行っていらっしゃいましたね。70年代にアメリカへ進出し、現地生産を行った日本の自動車メーカーと同じやり方という印象を持ちました」と飯尾愛一郎さん。「今後も、こうしたフランスで活躍されている方の講演会に出てみたいと思っております」
「私は会社経営をしております関係で、経営や海外事業に興味があります。味の素さんのような大企業とは経営方法なども、もちろん異なりますが、参考になる部分もたくさんございますので、ぜひまた参加させていただければと思っております」と飯尾まさ代さん。

お二人目は、趙 采薇 (チャオ ツァイウェイ)さん。ご出身は台湾だそうです。日本の大手PR会社で、日本の公共政策及び政府関係の研究をされておられます。
本日参加されたきっかけは、仕事上で知り合った在日フランス企業の方からの紹介でした。今回の講演会の内容を知って、本日初めてパリクラブのイベントに参加されたとのこと。
「日本企業がフランスやヨーロッパへ進出し、どのように事業展開をしていくのかがよくわかった講演会でした。大変意義深い講演会でした。実は、以前パリで仕事していた際、味の素さんのパリオフィスへ訪問したこともあるんです。これからもビジネスや文化関係のイベントがあれば、また参加したいと思います」

次に、グロワン・クレモンさん。
世界に数多くのレストランや食料品店を展開する大手企業にお勤めになっていらっしゃいます。
「弊社は在日フランス商工会議所から今回のテーマの告知があり、味の素さんも食品メーカーだったので、面白いと思い参加しました。地元企業との提携やその問題点、撤退の際のお話など、何十年にわたって培ってきた事例が聞けて、大変興味深かったですね。自分の勉強のためにも、今回のような食品関連の講演会やイベントには参加していきたいと思っています」

最後は、ジャン・バルテルミーさん。「味の素の海外戦略、特に欧州戦略に関する三宅氏のプレゼンテーションは当該事業部とパートナーの競争優位の進展という意味で大いに示唆に富んでいたと思います。欧州でのジョイントベンチャーのパイオニアである味の素は永年にわたってパートナーシップを評価し続けてきました。これらの意思決定に関する説明を味の素内部の人からお聞きすることができたのは魅力的でした。アグロ・食品セクターを超えて、これらの学びは欧州での成功にとって価値あることだと考えます」


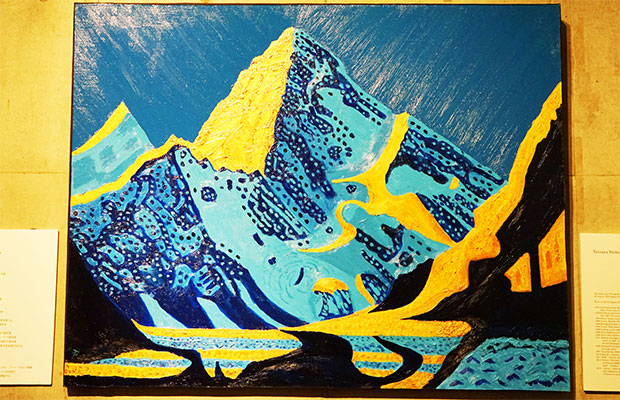
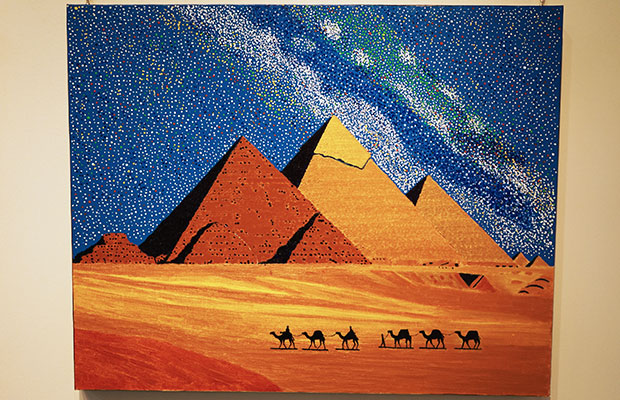
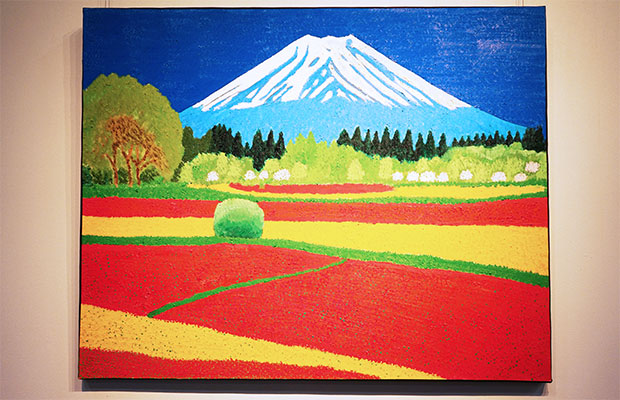









 食に関して、経済状況はどのような影響を及ぼしているのか?それを語るには、人・モノの動きが食に与えるある種の新しい変化に注目する必要がある――と語る久保氏。氏の話す「経済」とは、「人の動きが食に及ぼすダイナミックな影響」と言い換えてもいいのかもしれません。
食に関して、経済状況はどのような影響を及ぼしているのか?それを語るには、人・モノの動きが食に与えるある種の新しい変化に注目する必要がある――と語る久保氏。氏の話す「経済」とは、「人の動きが食に及ぼすダイナミックな影響」と言い換えてもいいのかもしれません。